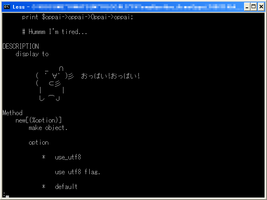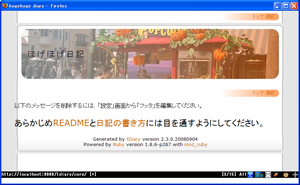mattn's nicodown at master — GitHub
http://github.com/mattn/nicodown/tree/master
適当だけど書いてみた。
タイトル取って来る所はlibxml使うの面倒臭かったのでXMLパーサ使わずベタで(実態参照文字あると変になるので気を付けて)。Windowsの場合だけWin32 APIでシフトJISにファイル名を変換しています。
荒いコードなので色々直し所がありますが、サンプルって事で。
//#define CURL_STATICLIB
#include <curl/curl.h>
#define HEX_DIGITS "0123456789ABCDEF"
#define IS_QUOTED(x) (*x == '%' && strchr(HEX_DIGITS, *(x+1)) && strchr(HEX_DIGITS, *(x+2)))
static char* response_data = NULL; /* response data from server. */
static size_t response_size = 0; /* response size of data */
static void
curl_handle_init() {
response_data = NULL;
response_size = 0;
}
static void
curl_handle_term() {
if (response_data) free(response_data);
}
static size_t
curl_handle_returned_data(char* ptr, size_t size, size_t nmemb, void* stream) {
if (!response_data)
response_data = (char*)malloc(size*nmemb);
else
response_data = (char*)realloc(response_data, response_size+size*nmemb);
if (response_data) {
memcpy(response_data+response_size, ptr, size*nmemb);
response_size += size*nmemb;
}
return size*nmemb;
}
int
main(int argc, char* argv[]) {
CURLcode res;
CURL* curl;
char error[256];
char name[256];
char data[1024];
char* buf = NULL;
char* ptr = NULL;
char* tmp = NULL;
FILE* fp = NULL;
int status = 0;
// usage
if (argc != 4) {
fputs("usage: nicodown [usermail] [password] [video_id]", stderr);
goto leave;
}
// default filename
sprintf(name, "%s.flv", argv[3]);
curl = curl_easy_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_ERRORBUFFER, &error);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, curl_handle_returned_data);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookies.jar");
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookies.txt");
// login
sprintf(data, "mail=%s&password=%s&next_url=/watch/%s", argv[1], argv[2], argv[3]);
curl_handle_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://secure.nicovideo.jp/secure/login?site=niconico");
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
res = curl_easy_perform(curl);
if (res != CURLE_OK) {
fprintf(stderr, error);
goto leave;
}
buf = malloc(response_size + 1);
strcpy(buf, response_data);
if (strstr(buf, "id=\"login_bar\"")) {
printf("%s\n", buf);
free(buf);
fprintf(stderr, "failed to login\n");
goto leave;
}
free(buf);
curl_handle_term();
// get video url, and get filename
sprintf(data, "http://www.nicovideo.jp/api/getthumbinfo?v=%s", argv[3]);
curl_handle_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, data);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 0);
res = curl_easy_perform(curl);
if (res != CURLE_OK) {
fprintf(stderr, error);
goto leave;
}
buf = malloc(response_size + 1);
strcpy(buf, response_data);
ptr = strstr(buf, "<title>");
if (ptr) {
ptr += 7;
tmp = strstr(ptr, "</title>");
if (*tmp) {
*tmp = 0;
strcpy(name, ptr);
}
#ifdef _WIN32
{
UINT codePage;
size_t wcssize;
wchar_t* wcsstr;
size_t mbssize;
char* mbsstr;
codePage = CP_UTF8;
wcssize = MultiByteToWideChar(codePage, 0, name, -1, NULL, 0);
wcsstr = (wchar_t*)malloc(sizeof(wchar_t) * (wcssize + 1));
wcssize = MultiByteToWideChar(codePage, 0, ptr, -1, wcsstr, wcssize + 1);
wcsstr[wcssize] = 0;
codePage = GetACP();
mbssize = WideCharToMultiByte(codePage, 0, (LPCWSTR)wcsstr,-1,NULL,0,NULL,NULL);
mbsstr = (char*)malloc(mbssize+1);
mbssize = WideCharToMultiByte(codePage, 0, (LPCWSTR)wcsstr, -1, mbsstr, mbssize, NULL, NULL);
mbsstr[mbssize] = 0;
sprintf(name, "%s.flv", mbsstr);
free(mbsstr);
free(wcsstr);
}
#endif
}
free(buf);
printf("downloading %s\n", name);
curl_handle_term();
// get video url
sprintf(data, "http://www.nicovideo.jp/api/getflv?v=%s", argv[3]);
curl_handle_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, data);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 0);
res = curl_easy_perform(curl);
if (res != CURLE_OK) {
fprintf(stderr, error);
goto leave;
}
buf = malloc(response_size + 1);
strcpy(buf, response_data);
ptr = strstr(response_data, "url=");
if (!ptr) {
free(buf);
fprintf(stderr, "failed to get video info\n");
goto leave;
}
tmp = strstr(ptr, "&");
if (tmp) *tmp = 0;
tmp = ptr;
while(*tmp) {
if (IS_QUOTED(tmp)) {
char num = 0;
sscanf(tmp+1, "%02x", &num);
*tmp = num;
strcpy(tmp + 1, tmp + 3);
}
tmp++;
}
strcpy(data, ptr + 4);
printf("URL: %s\n", data);
free(buf);
curl_handle_term();
// download video
fp = fopen(name, "wb");
if (!fp) {
fprintf(stderr, "failed to open file\n");
goto leave;
}
curl_handle_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, data);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 0);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, fwrite);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, fp);
res = curl_easy_perform(curl);
fclose(fp);
if (res != CURLE_OK) {
fprintf(stderr, error);
goto leave;
}
leave:
curl_handle_term();
curl_easy_cleanup(curl);
return 0;
}
確認はWindowsでしかしてませんが、きっとUN*Xでも動くはず。perlやpythonやruby使わない派の方は雛形として持ってって下さい。 UNIXプログラミングの道具箱: プロフェッショナルが明かす研ぎ澄まされたツール群の使いこなし
UNIXプログラミングの道具箱: プロフェッショナルが明かす研ぎ澄まされたツール群の使いこなし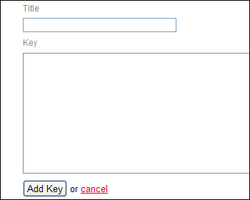
 集合知プログラミング
集合知プログラミング WEB+DB PRESS Vol.47
WEB+DB PRESS Vol.47